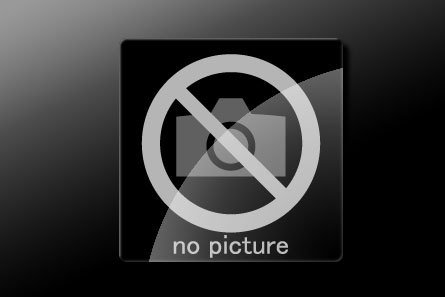
由緒:島原住吉神社は、もと島原中堂寺町の住吉屋太兵衛の自宅で祀っていた住吉大明神が、 霊験あらたかにして良縁の御利益があり、参詣者夥しきため、 享保十七年(1732年)祭神を島原の西北に遷座し建立されたものである。 その規模は、南は道筋(どうすじ=島原中央の東西道)から、 北は島原の北端にまで及び、広大な境内地を有した。爾来島原の鎮守の神として崇められ、 例祭と共に、太夫・芸妓等の仮装行列である「練りもの」が盛大に行われた。
ところが、明治維新後のj廃仏毀釈により、神社株を持たない当社は廃社となり、 祭神を歌舞練場内に祀る事となった。
しかしながら、地元の崇敬心は篤く、明治三十六年(1903年)には、 船井郡本梅村から無格稲荷社の社格株を譲り受け再興した。ただし、 現在の狭い境内地となり、正式社名も住吉神社は認められず、稲荷神社とされた。
平成十一年(1999年)には、社殿、拝殿を改修のうえ、社務所も新築し、 境内の整備がなされた。同十三年には、懸案の社名を島原住吉神社に改称し、 旧に復することとなった。
祭神:
例祭日:
祭神:
例祭日:
京都市下京区の有名神社:
